発達障がいがある幼児は治るの?
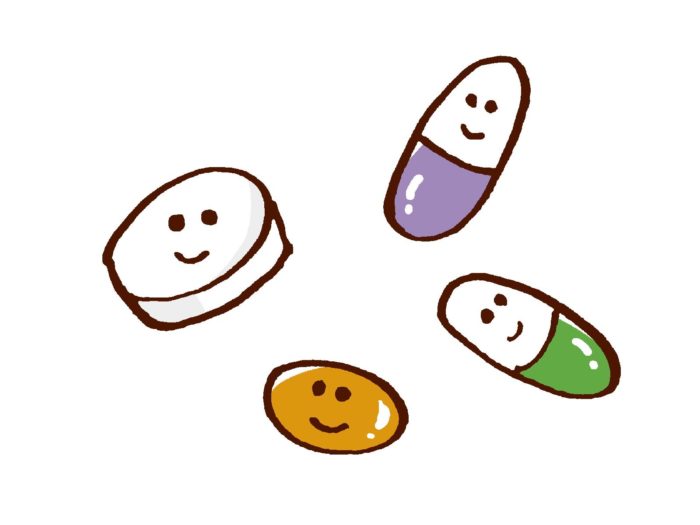
こんにちは
お子さんの発達が気になるお母さんの味方
感覚チューニストのゆうです。
「お子さんには、発達障害の疑いがありますね。」と、医師から言われたら……。
一瞬、耳を疑いませんか?
医師の言葉を理解しようとしながら、同時にお子さんのこれまでの様子やこれから先のことが一気に頭に押し寄せて、大変なショックと混乱に包まれるのではないでしょうか。
私は、そうでした。
それが、例えば乳幼児検診だったとしても、「発達が気になりますね……。」と言われたら、「え?何それ!発達?発達障がいってこと?」と、動揺したのではないかと思います。
突然、「発達」なんて言葉を聞いたら、「我が子がどうかしているの?どこが?何が?治るの?治らないの?何なの?」と混乱しますよね。
あなたも今、疑問と不安と心配と……混乱されているのでありませんか?
でも、安心してください、大丈夫ですよ。
なぜなら、私はその不安を安心に変えることができて、今日に至っているからです。
今回は、それをあなたもお伝えしようと思います。
それでは、幼児の発達障がいは治るのか、をテーマにお送りしてまいりますね。
Contents
発達障がいは幼児なら治るの?
幼児の発達障がいは治るのか治らないか、ということをお伝えする前に、「発達障害」について少しお話ししたいと思います。
「発達障害」は医師によって診断され、先天性もしくは幼児期の疾患や外傷の後遺症によって起きる、中枢神経系の脳機能の障がい、と言われています。
私は当初はこれを、とてもとても深刻な大問題と捉えていました。
でも、信頼するかかりつけ医による説明を受けたり、発達障がい専門のカウンセラーに相談にのっていただいたり、先輩お母さんの話を聴いたりするうちに、気持ちが変わってきたのでした。
今では我が子について「生まれつき又は幼児期の病気やケガの後遺症で、脳の働きに偏りがあるんだよね~。」という感じに、やわらかい雰囲気で受け止めています。
だから私は、「ハッタツショウガイ」という言葉を耳にしたり自分で言ったりするときには、「発達障害」ではなく「発達障がい」としているわけです。
今回は、私がこれまでに医師や心理士とのやり取りを通して、発達障がいについて整理してきた知識をもとに、幼児の発達障がいは治るのか治らないのか、についてお話をしてまいりますね。
発達障がいは病気なの?
さて、それでは改めて、発達障がいは病気なのでしょうか?
先ほどお話ししたように、発達障害は幼少期の病気が原因だったかもしれませんが、それによって脳の機能に何らかの障がいがある、ということなので、病気ではありません。
また、残念ながら現代の医学では治らないと言われています。
薬を飲んだり……、注射をしたり……、手術をしたら……、根本的に治る!といった種類の病気とは違うのです。
「病気じゃない……しかも治らない……。」
私は、かつてはひどく落胆しましたが、「根治しない」という表現に「持病があって一生薬が手放せない方もいらっしゃる……。」と思い直し、落胆から浮き上がった記憶があります。
また、私を含め発達障がいについて良く知らなかった人が、「まわりの人の接し方や本人の性格などが原因なのでは?」という見方をすることもありましたが、それも全くの見当違いだったので、ここでお伝えしておきますね。
発達障がいの「疑い」なら
さて、「治らない」と言われている発達障がいですが、それが発達障がいの「疑い」であれば、「治る」というよりは「疑いがあっただけだった」という方向になっていく可能性はあります。
また、発達のことに詳しい医師や、最新の診断基準をもとに診断されている医師なら、診察しても何の診断材料もない段階で「発達障害」とは口にされないとと思います。
私の経験からですが、発達について何らかの診断をくだすまでに、医師は本当に沢山の診断材料を時間をかけて吟味してくださいます。
「脳の働きに偏りがあるのは変わらないけれど、成長とともにその偏りの具合は変化していくかもしれないからね。」
「例え脳の働きに偏りがあったとしても、そのことが原因で家庭生活や学校などの集団生活で困ることがなかったり、将来的に社会で生きていく時に特に何かに困ってしまうような支障がなければ、『障害』とはならないからね。」
というお話をしてくださったこともあります。
だから、あなたのお子さんについてもきっと、これから成長していく過程も視野に入れて、脳も発達していくということも考慮して、注意深く検討してくださることでしょう。
つまり、幼児の段階に限らず、発達障がいの可能性が考えられたとしても「疑い」という診断であれば、将来的には何の診断名も必要なくなるかもしれない、ということになります。
発達障がいの診断が出ているなら
一方で、発達障害の診断が出ている場合であれば、繰り返しになりますが、残念ながら治ることはないと言えるでしょう。
冒頭でお話したように、発達障害は脳機能の障がいと言われていて、現代の医学では「治る」ものではないからです。
だから、信頼できる医師のもとで診断が出たのであれば、今後の医学の進歩に大いに期待しながら、ひとまず付き合っていくことになりますね。
ただ、脳の機能の偏りは治らないけれど、それによって生じている心身症状に対しては薬があるのです。
頭痛や腹痛、気分不良、眠れない、起きられない、衝動的な行動がある、落ち着かない等々の症状は、薬の作用で軽減させたり解決できることがあるからです。
また、日常生活や集団生活の様々な場面で、一般的に当たり前のように出回っている方法や手段が、お子さんに合わなくて太刀打ちするのが難しいのであれば、お子さんに合った工夫やアレンジで切り抜けていけばいいことになります。
根本的な解決にはなりませんが、対処・対応・対策はたくさんありますので、それによって毎日をよりスムーズに過ごすことは出来るようになるわけですね。
今のあなただからできる3つの大事なこと
いかがでしたか?
発達障がいについて、また発達障がいは治るのかどうかということについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。
でも、何をどうすれば切り抜けていけるのか、どんな対処・対応・対策があるのか、何も分からない段階では不安なままですよね。
それは、幼児の段階で発達障がい「疑い」の診断が出ている場合であっても、年齢が高くなってからの場合でも、同じ気持ちだと思います。
「治らないなら治らないで、この先どうしたらいいの?」
「疑いの段階だけど、これからどうすればいいの?」
まだまだ心配は尽きませんよね。
そこでここからは、そのような疑問をお持ちのあなたに、私が医師との会話を通して発達障がいについて理解を深め心に留めてきている、大事なことをご紹介したいと思います。
我が子が、発達障がいの疑いがあると言われたのは、幼少期ではありませんでした。
中学校高校と学年が上がるにつれて、いつの頃からか腹痛や頭痛に悩まされるようになっていたので、その症状について医師とともに様子をみていた頃のことです。
その時に、私が医師から聞いた内容が、これからご紹介する「3つの大事なこと」なのです。
これについて私は、何年たっても、また発達が気になるか否かに関わらず、我が子との関わりにおいて大変重要で、私と我が子の笑顔のために欠かせないことだと実感しています。
「3つの大事なこと」を心に留めておくことができたら、あなたとお子さんの将来もきっと明るく笑顔があふれるに違いないと信じています。
あなたとお子さんがどんな段階にあっても、今のあなたにきっと役立つと思いますので、ぜひお読みくださいね。
大事なこと1.お子さんが自分を肯定できるようにしてあげる
大事なことの1つ目は、「お子さんが自分を肯定できるようにしてあげる」ということです。
これは、医師による「大事なのは成功体験なんですよ。」という言葉からきています。
これは、医師が我が子について、発達障がいを視野に入れた見立てをされた後に、発達障がいに関係することとして、私が初めて耳にした医師の言葉でした。
「発達障がいがあるとすると、もともと自分を肯定しにくいっていう特性があるんです。それは責めるところでもなくマイナスなことでもなく、そういうものなんです。」
「これまでにも、自分をまわりと比較して否定してきていたかもしれないんです。それによって、益々自信がなくなっている可能性があります。」
「だから、これからは成功体験をたくさんさせてあげることが大切なんです。」
いかがでしょうか。
あなたやお子さんが置かれている状況や、お子さんの症状は、我が家のそれと同じではないと思います。
でも、「自分を肯定できるようにしてあげる」ということは、どのお子さんに対しても共通する大事なことではないでしょうか。
今から自己を肯定できるようにしてあげながら成長を見守るか、自分のことを否定しがちなお子さんを更にけなして否定しながら育てていくか、あなたはどちらを選びたいですか?
大事なこと2.お子さんを否定しない
次にご紹介したい大事なことは、「お子さんを否定しない」ということです。
医師の言葉を交えてご説明いたしますね。
「あれはダメ!これは出来ていない!と、否定したりダメ出しをするのはなく、自分を肯定できるように自信が持てるようにしてあげることが大事です。」
自分を否定してダメだと思いがちなお子さんに対して、さらに追い打ちをかけて親が否定する必要なんて、どこにもありませんよね?
医師が、我が子に限らず発達障がいの可能性がある子供の将来について、その幸せな将来を思って厳しい口調でつぶやいた言葉があります。
「否定して育てるということは……子供の将来をメチャクチャに壊したいのか!!ということなんです……。」
これが、沢山の症例を診てきた医師の言葉です。
お子さんの将来を壊したくない……これに気がつくのは、今からでも遅くないはずです。
お子さんの明るい将来、長い人生はこれからやってくるのですから。
私は、我が子と私のスタートは決して遅くなかった!と、確信しています。
なぜなら、笑顔になって自分のペースで幸せに向かって歩んでいるのを、我が子も私も一緒に実感する日々だからです。
大事なこと3.お子さんの苦手なことや不得意なことはカバーする
3つ目の大事なことは、「お子さんの苦手なことや不得意なことはカバーする」ということになります。
「え?子どもが出来ないことは、できないままでいいの?」
「親が手伝ってあげちゃっていいの?」
と疑問を持たれましたか?
大丈夫です。
これにも、医師からの説明が裏付けとしてありますからね。
「今のところ、またはこれまで出来ていたことは、本人の中の出来ることや得意なことで、そうではないところをカバーして、こなせているということだと思いますね。」
「周囲の人の関わりや環境が変わったりすると、本人が持っている能力というか力ではカバーしきれなくなっていく、という可能性があります。」
「その時は、まわりの人がカバーしてあげて、出来るようにしてあげることが大切なんですよ。」
いかがですか?
お子さんの苦手なことや不得意なことは、あなたが手伝ってあげればいいわけですね。
もしかして、
「まだ小さいうちから、手助けばかりしてしまったら、大きくなって自分で出来るようになるの?」
「苦手なことがあっても、将来は結局自分でやっていかないとならないんだから、難しいことでも今のうちから向き合わせておかないと……。」
と、お考えになりましたか?
もしそうであれば、以下の医師の言葉を読んでみてください。
「苦手なことや不得意なところを、本人が意識できるようになれば、本人自ら別の方法でカバーできるようになっていけますよ。また、まわりがカバーしてあげるとか、配慮してもらうとか、そういう対処も必要になりますね。」
「発達障がいがあることが原因で、苦手とか不得意があるということは、サボっているとか怠けているとか、気合いが足りていないということではないから。」
「ハードな練習をしても、繰り返し繰り返し訓練をしても、難しいものは難しいんだから、かえって逆効果なんですよ。」
「だって、苦手だから難しくて出来ないっていうのが根底にあるわけだから、自信がなくなるばかりでしょ?」
医師の説明に私は、心から安心したのを覚えています。
何故なら、まさに医師の言葉通り、我が子に対して「怠けているだけでしょ!」「やらなくちゃ!っていう自覚がないんだよ!」という言葉を投げかける人もいたからです。
あの子の様子に、「やる気がない」なんて言う人は間違っているんだ!
「あの子は自分でやらせないとダメになってしまう!」なんて考えなくていいんだ!
あの子が今、自分でできないところは手伝ってあげて、助けてあげて大丈夫なんだ!
あなたも是非、お子さんの苦手なことや不得意なことに対して、迷うことなく手を差し伸べてあげてくださいね。
お子さんはきっと、これから成長していくにつれて、あなたの力だけに頼るのではなく、お子さん自らの工夫でカバーして太刀打ちできるようになったり、自分からまわりの人に協力をお願いしたりできるようになることでしょう。
ただ、今はまだ、小さいお子さんご本人もあなたも、お子さんは何が苦手で不得意なことなのかが良く分からないと思います。
お子さんが自分のことを言葉で上手く説明することはまだまだ難しく、幼いからこそ出来ないことの方が多いからです。
その場合には、日頃のお子さんの様子をメモしておかれることをお勧めします。
なぜなら、医師の診察やお住まいの市町村で検診がある時などに、専門家に日頃のお子さんの様子を伝えられるからです。
それが貴重な情報源となり、専門的な立場の方もアドバイスがしやすくなるのです。
そんな……何をメモしたらいいか分からない……。
って思われましたか?
心配はいりませんよ、なんにも堅苦しく考えなくて大丈夫です。
お子さんが出来ることや出来ないことはもちろん、あなたが大変だと思うことや楽だなと感じることなど、気がついたことでいいのです。
「多分○月○日……抱っこが好きじゃないみたい、あんまり甘えてこないし、あんまり泣かない……楽かも!」
「○歳○ヶ月頃……泣いてばかり、着替えで大騒ぎ、不機嫌なことが多くて本当に大変!」
母子手帳に書いたり……、専用ノートを作って書いておいたり……、スマホにメモしておいてもいいし……。
あなたが記録しやすいスタイルで、あなたに余力がある時にメモしておけば大丈夫ですよ。
あなたと一緒にお子さんを見守り支えていく方々にとって、その時点のお子さんからは見てとれない様子のメモは、他の何からも得られない貴重な情報に違いないのです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、発達障がいがある幼児は治るのか、ということをテーマにお届けしました。
現段階の医学では治らないとされている発達障がいですが、 お子さんと関わる方が早くからそれを理解して、 お子さんにとって適切な対応・対処をすることで、 将来的に困ることを軽減させることが可能です。
そうしたら、お子さんは笑顔いっぱいに成長していけるのではないでしょうか。
その成長を、発達障がいという一つの見方にとらわれることなく、 見守って支えて応援していきたいですね。
それでは、今回はこちらで失礼いたします。
最後までお読みくださって、どうもありがとうございました。
感覚チューニスト ゆう


